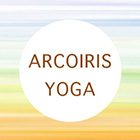FC2ブログでの本の紹介(備忘録)を、少しづつこちらのヨガのHPにお引越しします。
追々しようと思っていましたら、後回しになり月日が経過してしまい・・・。
本当は映画紹介もお引越ししたいのですが、これはまた先になりそうです。
いったいいつになりますでしょうか。
今から12年前の2010年の感想は我ながら気恥ずかしく、
正直なところ手直ししたい気持ちでいっぱいなのですが、あえてのそのままで。
ただ絵文字などの装飾は消し、色付きの文字は黒色に、当時の訃報は時系列を変更しました。
ここ1~2ヶ月ほど、昔読んだ本の話が続きますが、
「いつの時代のことなのかしらと」驚かれませんように、ごゆるりとおつきあいくださいませ。
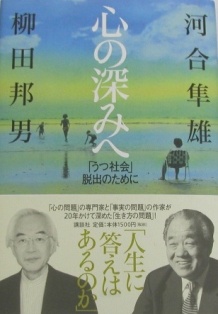
心の深みへ 「うつ社会」脱出のために 河合隼雄・柳田邦男 講談社
「真の幸せ、幸福とは?」
「たましい」や「心」というものに関心のある人は、きっとぐいぐい引っ張られる臨床心理学者・河合隼雄さん、ノンフィクション作家・柳田邦男さんによる、7章からなる対談集です。
私たちの心の満たされぬもの、そして満たされないからこそ、どうしたらよいのだろうか、ということが、二人によって率直に語られています。
ここでいきなりですが、ヨガ(ヨーガ)の考えに基づく「幸福」のとらえ方です。
ヨガでの「幸福」とは、常に「自分の内」にある、と考えられています。
1 集中状態
2 ゆっくりとした心理作用
3 内心の静けさ(無心さ)
以上の3つを満たしている時を「幸福」と呼びます。
幸福と不幸を同等のものとして見る。成功と不成功を同等のものとして見る。
結局のところ、幸福感はその人物・本人の心の状態に、強~く影響されるものです。
「幸福」というものは、「自分の外」にではなく、例えば、物質的な全ての品物、お金、名誉、仕事、
周囲の家族や友人や恋人にもなく、「自分の内」に見い出すものなのです。
「ヨガの考える幸福って・・・」と思われる方もいらっしゃる気がします。
まぁ、私も悟っているわけではないので・・・
この本「心の深みへ」によると、幸せは物質的なものや条件によるものではなく、
「幸せは自分の内にある」という非常にヨガ的なことを、二人が主張されていました。
偶然手にしたこの本に、ものすごいシンクロを感じ、とっても嬉しくなったのでした。
時にカウンセリングのようであり、「読んでよかった」という対談本でした。
強く印象に残った、4つのお話です。
1、精神科医で死後の霊的な世界に傾倒していったエリザベス・キューブラー=ロス博士の話。
(強靭な精神力。素敵です。)
2、英国の内科医でセント・クリストファー・ホスピスのシシリー・ソンダース博士の話。
3、先ごろ亡くなられた免疫学者の多田富雄先生の「記憶は(脳ではなく)胸に」という話。
4、柳田邦男さんの自殺され脳死状態になったご子息とご家族の話です。法律上では確かに脳死でしょうが、そんなに割り切れるものではありませんよね。
参考までに、7つ対談のお題です。
1「何が人を幸福にするかを描く」
2「生きにくい子どもの深層を探る」
3「息子の死を見つめて語る」
4「人が死ぬときに迫る」
5「心の環境問題に取り組む」
6「直面している生き方の問題を語り合う」
7「たましい」
<参考文献>
エリザベス・キューブラー=ロス
「死ぬ瞬間」”On Death and Dying”
「人生は廻る輪のように」”The Wheel of Life”
「永遠の別れ―悲しみを癒す智恵の書」”ON GRIEF AND GRIEVING:Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss”
2010年8月6日の感想