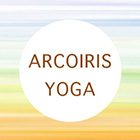学名:Tulipa L
英語:tulip
桜と同じくらいの時期、我が家のチューリップが咲きました。
茎が短く、イメージしているチューリップとちょっと違うような。
咲き方は、ぽっと一輪咲いて、よろっと枯れてきた頃、
また次の蕾だったものが咲きはじめるという調子で、長く楽しめました。
今は来年に向けて球根の光合成をしているところです。
あともう少ししたら、掘りおこします。
さて、どんな球根になっているのかしら。


チューリップ(英語: tulip)とは、ユリ科チューリップ属の植物。球根が出来、形態は有皮鱗茎。和名は鬱金香(うこんこう、うっこんこう)、中近東ではラーレ(トルコ語: lale、ペルシア語:など)と呼ばれる。アナトリア、イランからパミール高原、ヒンドゥークシュ山脈、カザフスタンのステップ地帯やキルギスが原産。(wikiより)
<学名ゆらい>
チューリップの語源はトルコの女性が巻くスカーフ「トゥルベント」(柔らかな布の意味)に由来し、それがラテン語で「トゥーリッパ」と呼ばれるうちに次第に「チューリップ」へ変化していったという説がある。(greensnapより)
<和名ゆらい>
和名は「鬱金香(うっこんこう)」。ウコンに似たほろ苦い香りがすることからこの名がついた。
<特徴>
春に咲く球根植物で、その球根は直径3cmほど、先が尖った玉ねぎのような形をしている。10月中旬~12月初旬までに植えると、3~5月にかけて開花する。
育てやすく、光沢のある花びらが太陽の光を受けてつややかに輝く、美しい花。よく見かける一重咲き以外にも、八重咲やユリ咲き、フリンジ咲き、切れ込みのある花びらがフリル状に捻じれながら咲くパーロット咲きなどさまざまな咲き方があり、約5,600以上もの品種があると言われている。(日比谷花壇より)
<種類・品種>
1)アプリコット・ビューティー
シンプルな一重咲きの早生種。淡いアプリコットカラーから、色味が深い部分はピンク色になる、色味の特に美しい品種。
2)バレリーナ
ユリ咲きの晩生種。赤橙に鮮やかなオレンジの縁取りで、バレエのチュチュのような独特のシェイプを持ったフォルムとともに目を引く。チューリップには珍しく良い香りがする品種。
3)チューリップアイスクリーム
八重咲の晩生種。花びらが幾重にも重なってモコモコと盛り上がり、中央からソフトクリームのように突き出てくるユニークな見た目のチューリップ。珍しく、存在感も抜群の高級品種。
4)チューリップ・ブラックヒーロー
八重咲きの晩生種。黒みがかった深い紫色の花びらで、光の当たり方で色味が変わる、ベルベットのような質感が印象的。ボリュームがあり、切り花としても人気がある。
5)ファンシーフリル
フリンジ咲きの晩生種。鮮やかなピンク色の花びらに、房飾り(フリンジ)のように白の縁取りがついた2色咲きのチューリップ。優しい印象で春らしさを感じさせてくれる。
6)フレミングパーロット
パーロット咲きの晩生種。花びらに入った深い切れ込みがフリル状になっている様子がオウムの羽根のように見えることから、パーロット(オウム)と呼ばれている。赤と黄色のストライプ模様が鮮烈な印象。(日比谷花壇より)



<花言葉>
博愛、思いやり(greensnapより)
愛の告白、美しい瞳(日比谷花壇より)
赤色 家族への感謝
ピンク色 労い
オレンジ色 照れ屋
紫色 気高
白色 待ちわびて(日比谷花壇より)
<過去関連記事>
・Arco Iris Yoga 2019年5月23日 トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美 国立新美術館→こちら
・Arco Iris Yoga 2024年2月28日 チューリップ1→こちら